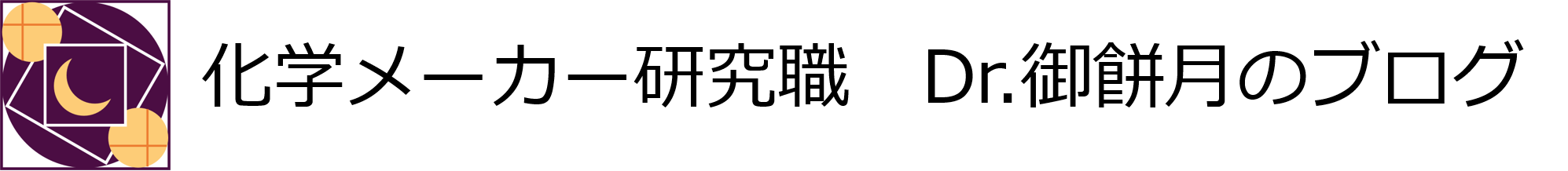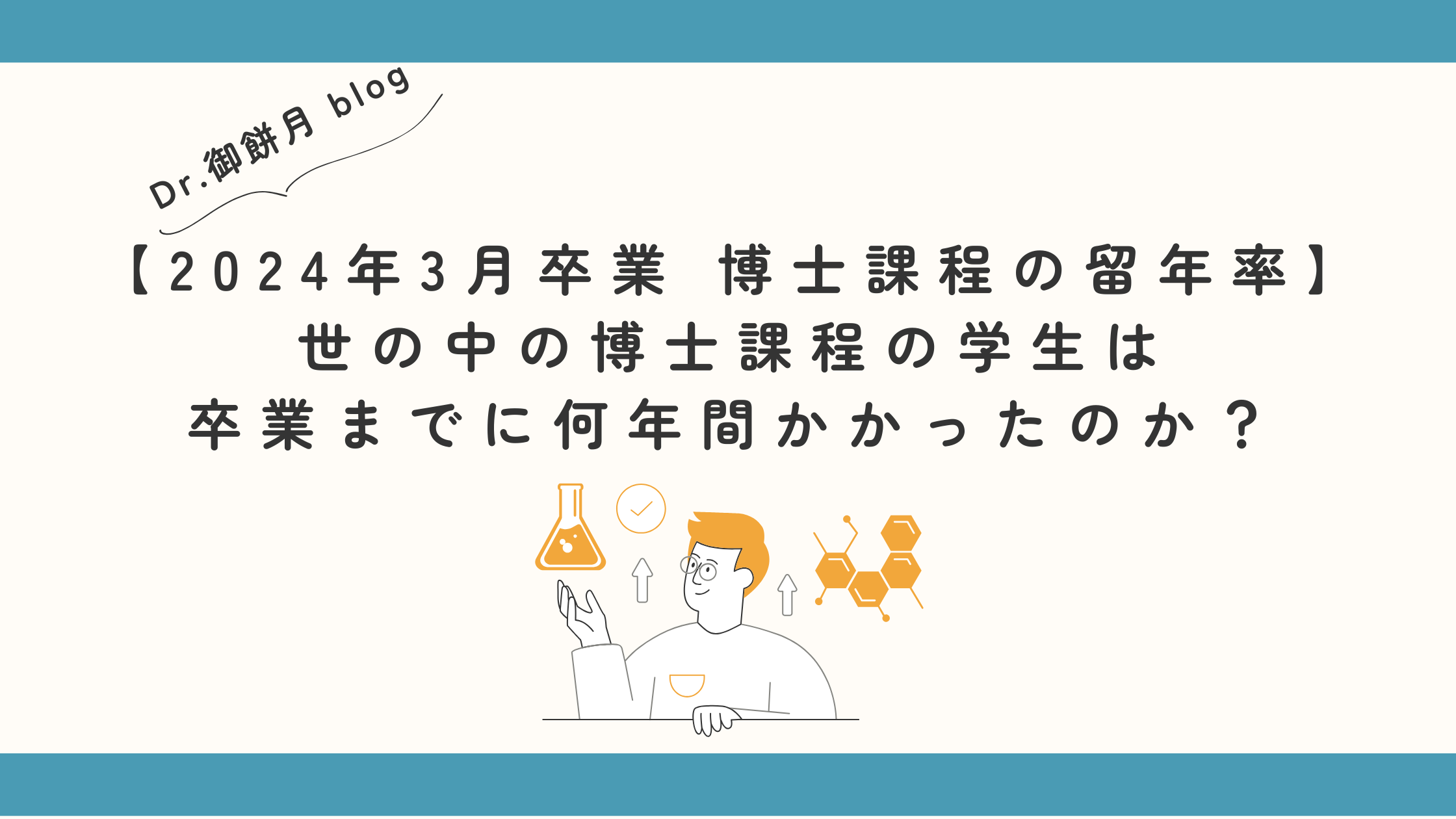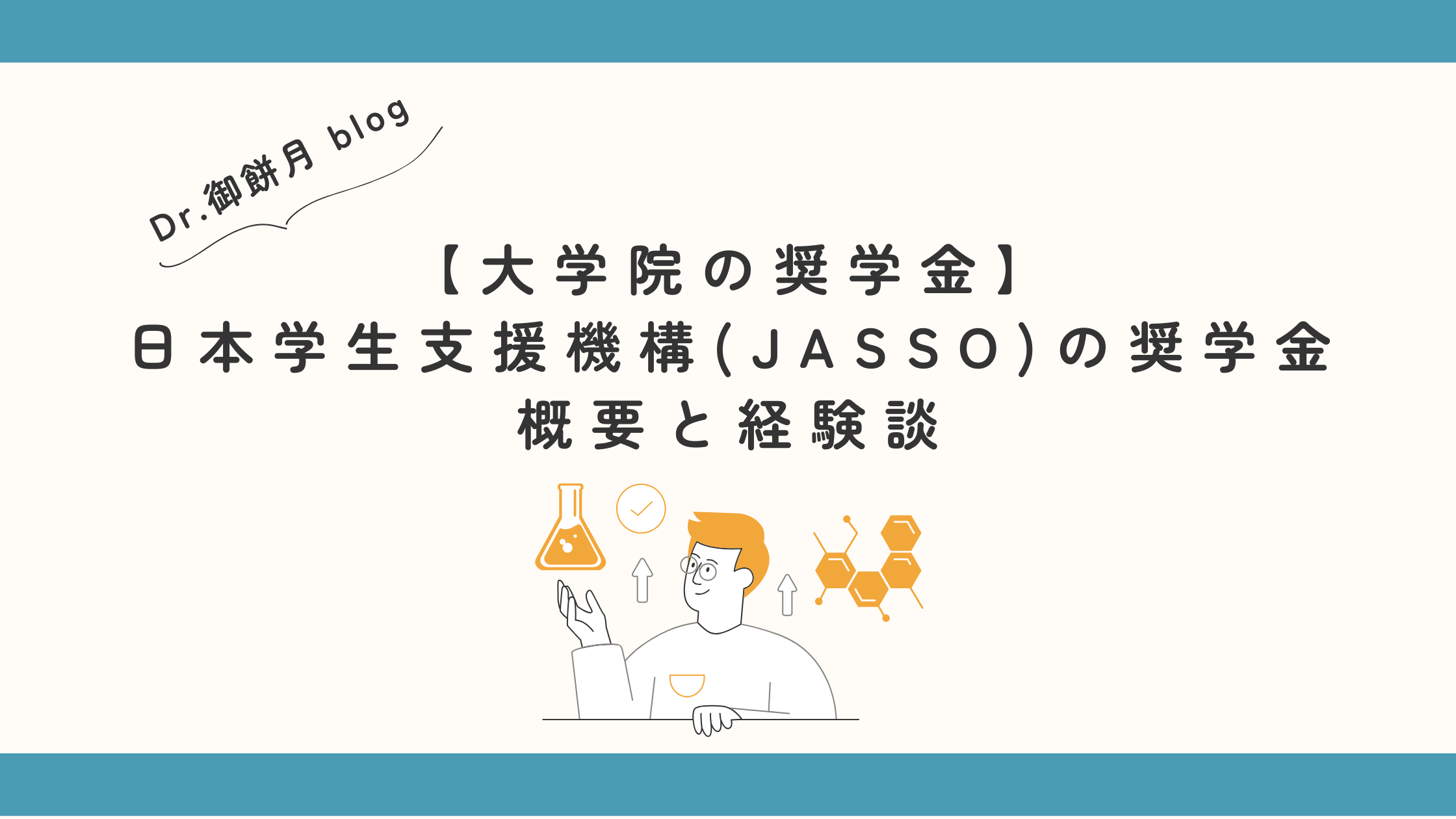学振ってなに?元学振特別研究員が博士課程進学者向けにDC1, DC2のメリット・デメリットをざっくり解説!
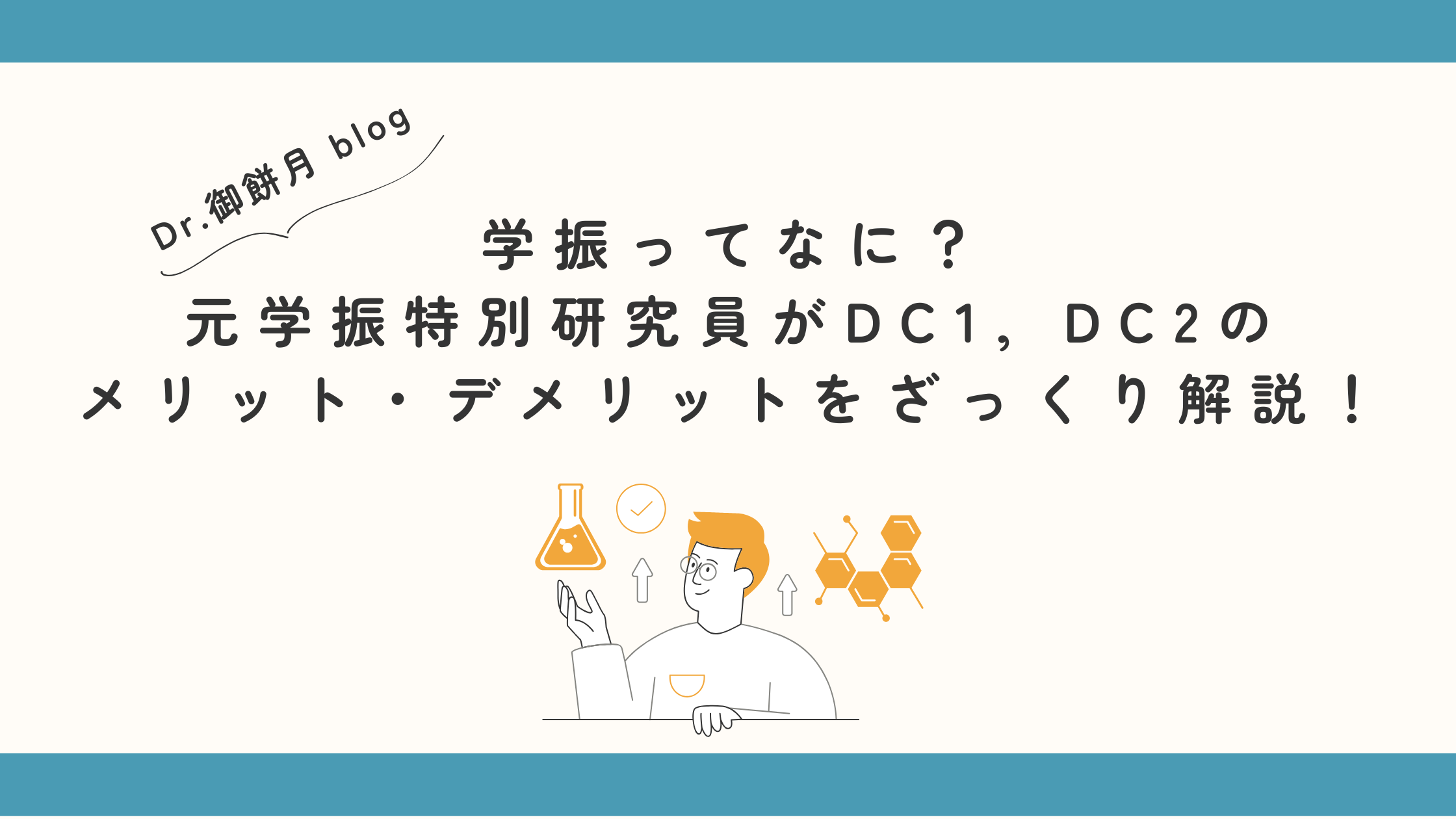
どうも、Dr.御餅月です!
本日は日本学術振興会 特別研究員 DC1、DC2について解説します。
私自身、学生時代にDC2に採用されていました。博士後期課程で実際にDC2制度の支援を受けながら、研究活動に専念していた経験を交えて解説していきたいと思います。
- 学振DC1, DC2の概要をざっくり知りたい方
- 博士課程に進学しようか迷っている学生の方
- 社会人ドクターとして博士課程に進学しようとしている方
結論
| DC1 | DC2 | |
|---|---|---|
| 採用期間 | D1~D3の 3年間 | D2 or D3からの 2年間 |
| 研究奨励金 (給与所得) | 月20万円 | |
| 研究費 | 最大年150万円 | |
| 採択率 (2024年度実績) | 15.1% | 17.1% |
日本学術振興会 特別研究員 DC1, DC2とは?

日本学術振興会 特別研究員制度の概要
日本学術振興会 特別研究員制度とはいったいどんな制度でしょうか。以下、日本学術振興会HPの引用です。
「特別研究員」制度は優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることにより、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的として、大学院博士課程在学者及び博士の学位取得者で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、支援する制度です。
要約すると、優れた能力を有する博士課程の学生や博士号取得者を、アカデミックの世界で研究に打ち込めるように支援する制度、ということになります。独立行政法人 日本学術振興会が運営している特別研究員制度であるため、この制度のことを「学振」と略して呼ぶことが多いです。(本記事でも学振と略します。)
学振では研究に専念するために日常生活に使える研究奨励金と、研究に使うための研究費を支給することで、経済面から採用者を支援してくれます。
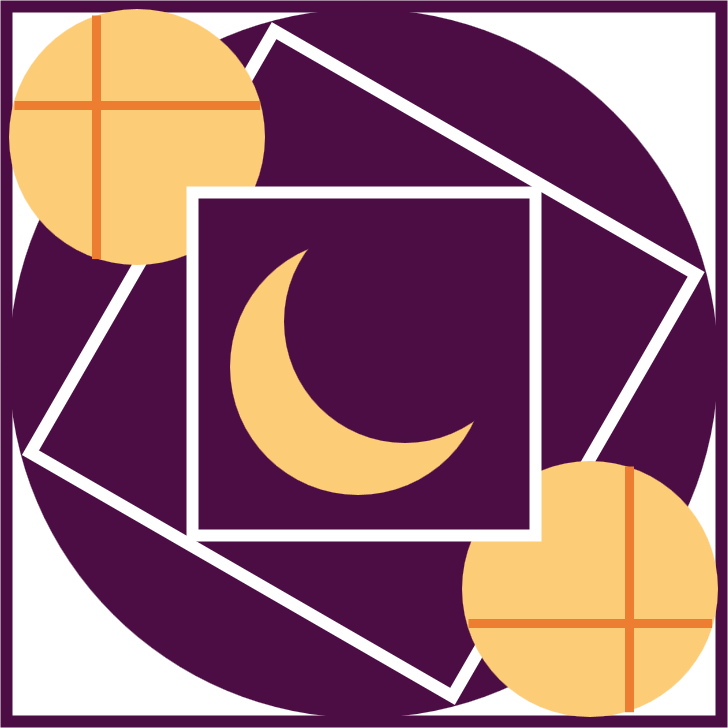
博士課程在学中に金銭的な援助があるのとないのでは、心理面で雲泥の差が生じます。ただでさえ卒業できるかどうか不明なのに研究に割く時間がアルバイトに奪われた時の心理的ダメージは大きいです!
学振には区分がいくつか存在します。
博士後期課程在学者を支援するDC1とDC2、ポスドク(博士号を取得し大学等研究機関の任期付き研究職)を支援するPD、RPD、CPD(2024年以降募集停止)があります。
本記事では博士後期課程在学者を支援するDC1とDC2の解説を行います。
学振 DC1とは?
DC1は博士課程1年目で採用される可能性がある方が応募できる学振です。具体的には修士課程2年生や社会人から進学する方が応募できます。採用後に始まる博士課程でやりたい研究を思い描きながら申請書を書くことになります。DC1の採択率は全体で15.1%、化学分野だけに着目すると15.6%と非常に低い採用率であることがわかります。
- 採用期間:3年間
- 研究奨励金(給与):月20万円
- 研究費:最大年150万円以内
- 採用率:15.1% (2024年度)
| 分野 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 | 計 |
| 申請者数 | 435 | 415 | 639 | 469 | 798 | 376 | 449 | 414 | 596 | 4591 |
| 採用者数 | 61 | 61 | 98 | 73 | 119 | 57 | 71 | 65 | 89 | 694 |
| 採択率 | 14.0% | 14.7% | 15.3% | 15.6% | 14.9% | 15.2% | 15.8% | 15.7% | 14.9% | 15.1% |
学振 DC2とは?
DC2は博士課程1年目、2年目の学生が応募できる学振です。したがって、修士2年生の後半で進学を決めた博士課程1年目や、DC1に応募したが採用されなかった博士課程2年目の学生が応募対象です。採用率は17.1%、化学分野に着目すると17.4%とこちらも採用率は非常に低いです。申請者数はDC2のほうがDC1よりも多く、このことから修士2年生の後半で博士進学を決めた学生が多いことがうかがえます。
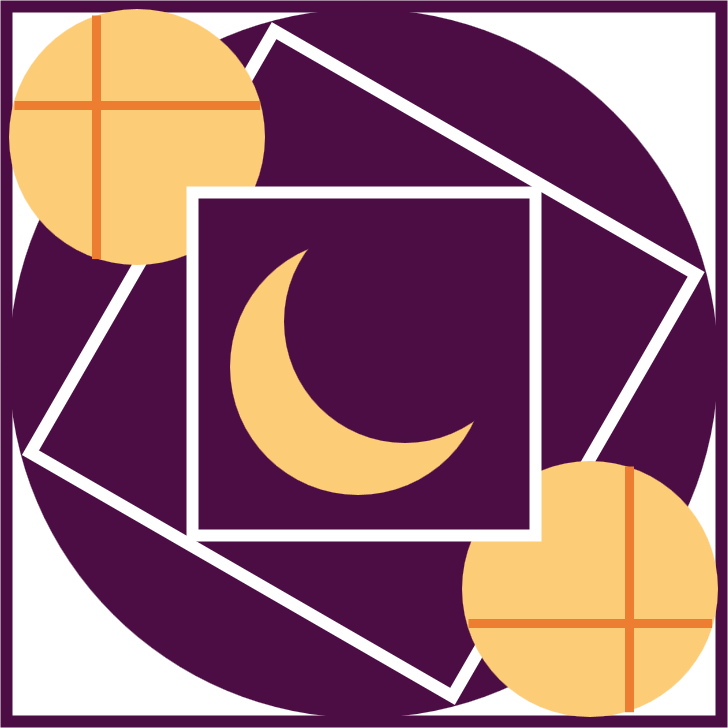
修士課程1年生の段階で博士課程進学を決めているのであれば迷わずDC1に応募しましょう。私は修士課程で就活をしてから進学を決めたため、学振に応募する機会を一回分失いました。。。
- 採用期間:2年間
- 研究奨励金(給与):月20万円
- 研究費:最大年150万円以内
- 採用率:17.1% (2024年度)
| 分野 | 人文学 | 社会科学 | 数物系科学 | 化学 | 工学系科学 | 情報学 | 生物系科学 | 農学・環境学 | 医歯薬学 | 計 |
| 申請者数 | 594 | 675 | 859 | 530 | 1216 | 509 | 524 | 578 | 882 | 6367 |
| 採用者数 | 102 | 113 | 148 | 92 | 205 | 88 | 92 | 99 | 152 | 1091 |
| 採択率 | 17.2% | 16.7% | 17.2% | 17.4% | 16.9% | 17.3% | 17.6% | 17.1% | 17.2% | 17.1% |
学振 DC1, DC2の応募の流れ
募集要項が公開されたら申請書のフォーマットを確認し、書類作成を始めましょう。申請書のメインとなる研究提案は何度も研究指導者とやり取りをしてブラッシュアップしていきましょう。
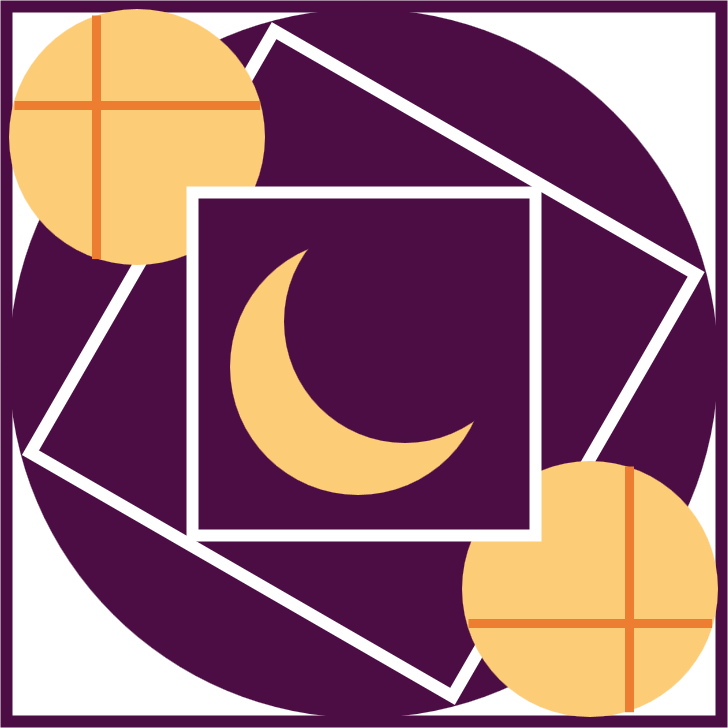
論文も分野によってお作法があるように、研究提案にも分野によってお作法があります。指導教員や研究室の先輩の協力を全力で仰ぎましょう。
ギリギリまで申請書を推敲したら、申請書を提出します。
応募者用のウェブサイトから提出できます。
何かをやれるのはここまでです。祈りましょう。
審査区分に応じた審査委員6人による書面審査
一段階目の書面審査の結果、ボーダーゾーンとなった申請者を対象に改めて書面審査を実施
採用者のうち大部分がこのタイミングで発表されます。
どういう基準で選ばれるかわかりませんが、一次選考結果で採用されなかった方の中から採用者が選ばれます。
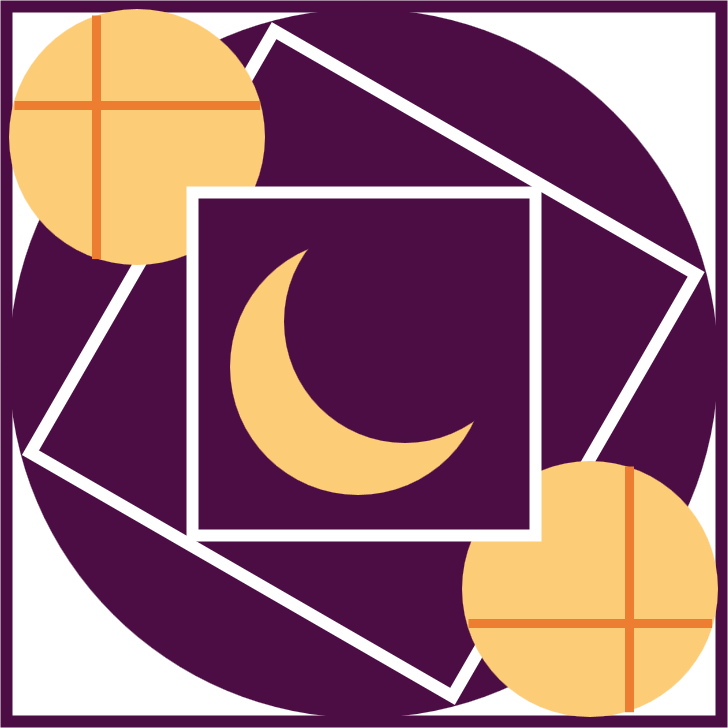
二次選考の基準も採用人数もよくわかりません。
同じ研究室の先輩は二次選考会としてポスター発表をしに行っていましたが、調べてもそんな情報出てきません。情報ください!
学振DC1, DC2のメリット・デメリットとは?

メリット1 | 生活費がもらえる
研究奨励金は普段の生活に使える給与所得です。わずかな時間でも研究に当てたい博士課程の学生にとっては、アルバイトをせずに研究に専念できるため大変ありがたいです。月20万円で生活費と学費を払うことを考えると決して余裕のある暮らしはできませんが、あったほうがいい決まっています。
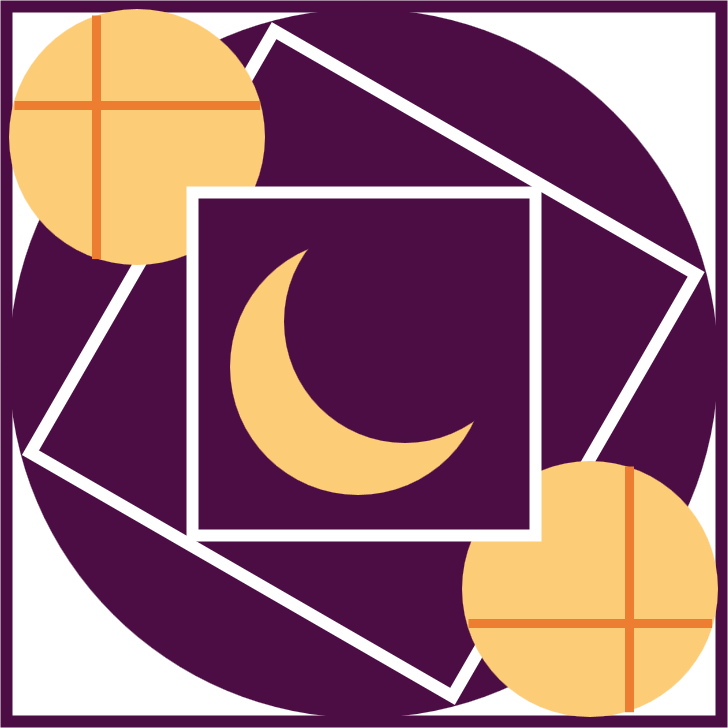
一昔前は学振採用者は学振以外の収入源を持つことは研究に専念していないとみなされたため、アルバイト禁止でした。
今は緩和されてアルバイト可能ですが、支給額は月20万円から改善されていません。改善待ったなしです。
メリット2 | 経歴に箔がつくため、就職で有利
学振は採用率が非常に低いため名誉職の側面を持ちます。学振の低い採用率を突破したということは、研究者として提案力がその世代の上位2割に位置していることを意味します。その事情を知っている企業の人事の視点に立って考えてみると、それは魅力的な人材に映ります。
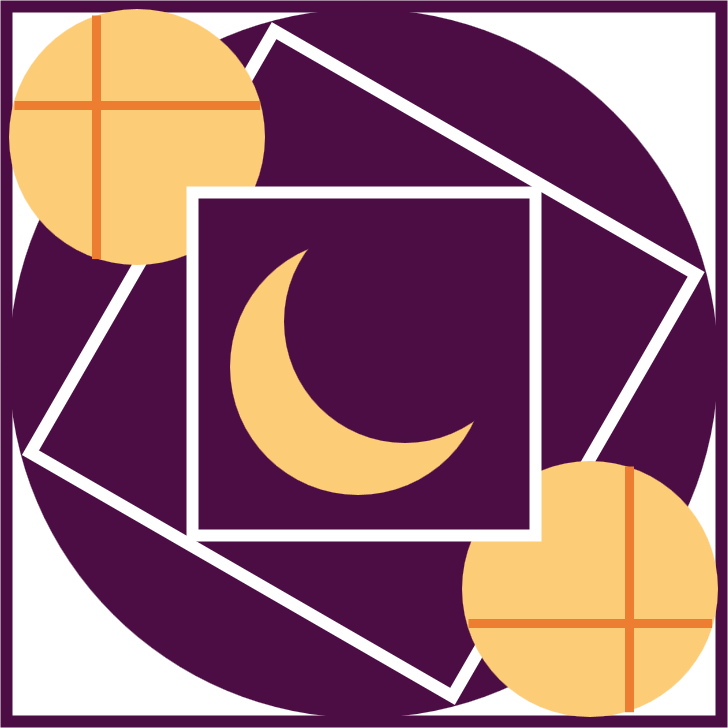
化学メーカーに就職した私も面接時に人事の方に学振のことを触れられました。
デメリット1 | JASSOの奨学金と併用できない
JASSO(日本学生支援機構)という機関が行っている奨学金制度を利用できなくなります。大学で奨学金といえばここから借りることが一般的で、ここからお金を借りることができれば学位取得までの見通しが立てられます。一方で、民間の奨学金は受領できるようです。奨学金の幅が狭まる点がデメリットです。
デメリット2 | 給与所得扱いの収入のため、親の扶養から外れる。納税・国保加入義務が発生する。
学振の研究奨励金は、奨学金ではなく給与所得として扱われるため親の扶養から外れます。したがって、所得税や住民税などの税金を払う必要があります。また、日本学術振興会は雇用主ではないらしく学振採用者は国民健康保険(国保)に加入する必要があります。したがって、月20万円をすべて受け取れるわけではありません。
給与を支給されている人(サラリーマン)は雇用主の指示に従って健保組合に加入します。給与を支給されていない人(フリーランスなど)は国保に加入します。これは税法上のグレーな部分ですが、、、学振採用者は給与所得を受け取りながら国保に入るという不思議な状態です。フリーランスのように雑所得であれば節税する方法はあるのですが、給与なので節税対策は限定的です。
デメリット3 | メーカーなど技術系企業でない限り知名度が低い
大学院に進学していると忘れそうになりますが、博士課程に進学している人はマイノリティ中のマイノリティです。そのため、学振のことを知っている一般の方はほぼいません。化学メーカーなどであれば人事の方も含めて学振を知っているので、就活の役に立ちます。一方で、金融系や商社系など理系卒の方があまり多くない企業では、知名度が低く経歴に華を添えるものではありません。咲く場所を選ぶ必要があります。
まとめ
今回は学振DC1、DC2について解説していきました。
私の意見ですが申請は大変な労力がかかりますが、メリットが多いように思います。メリットもデメリットもある学振ですが、博士課程に進学するのであれば迷わず応募しましょう!